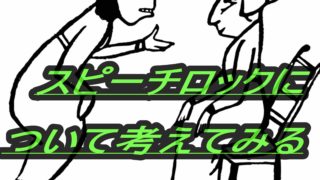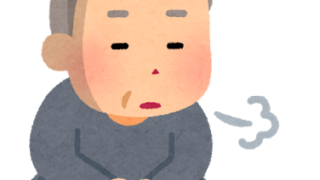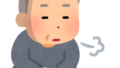みなさんこんにちは!こんばんは!ケンマルです。
その中には介護職に就く方もいらっしゃると思います。
知っておいて欲しい介護現場の現状
新聞やテレビなどで介護現場のニュースや番組を見ている方ならある程度分かると思いますが、現在の日本における介護の現場は常にマンパワー不足(人で不足)でその日の業務をこなすのも大変なのが現状です。
そういった状況の為、折角入って来た新人職員の指導もOJTなど行えず育成経験の少ない職員が指導に当たり指導する職員も転々とするという事です。
施設のよってはきちんと「新人教育マニュアル」があり指導にあたる職員にも教育がされているところもありますが、そういう施設はかなり稀でほとんどの施設ではその日その日で出勤した職員(新人教育の指導を受けていない)に新人が付くという形になっています。
その為、指導に当たる職員によって教わるケアの仕方や仕事の流れがまったく違ったりします。そういった背景から新人職員が「教えられたことと違う」とか「そんなこと教えてもらってない」など教育が統一されてないが故にその葛藤で苦しむことが多々あります。
教わる内容が先輩職員によって様々なのは介護士の人数だけ介護の方法・やり方があるためです。その為、新人介護士さんには現場に慣れるまでは「教ってる内容が人によって違う!」と悩むより「色々なやり方があるんだね」って割り切って肩の力を抜いて先輩の指導を受ける事をオススメします。
新卒介護士さんに知っていて欲しい学生の時と社会人になった時の現場の大きな違い 分からないことが分からないときの対処法!
学生時代と社会人との違い
学生の頃は学校や塾などで先生がきちんと道筋を立てて教えてくれたり、先生の方から分からないことや困っていることを聞いてくれる体制だとおもいます。
社会にでるとそこが大きく変わり、「分からないことは自分で調べる」「分からないことは自分から積極的に周りの職員や仲間に聞く」という形に変わります。簡単に言えば自主性が問われる環境になるわけです。
もちろん、社会人になっても新人の頃は先輩職員から指導をされます。そんななかで先輩職員も新人職員に対し「分からないことがあったら聞いてね」と言葉を掛けてくれると思います。
ただ、先輩職員も人手の少ない現場環境で通常業務をこなしつつ新人教育もしないといけないので新人職員が「どの部分が理解できていないか」「何を悩んでいるか」などきめ細かなところまで新人職員の状況を把握できないこともまります。
分からないことが分からない!そんなときの対処法
新人職員からすると「なにか分からないことがあったら聞いて」といわれても慣れない介護という環境のなかで自分自身が「なにが分からないかが分からない!」って焦ってしまいがちだと思います。
そういう時は先輩職員には「一度教わったことをまとめてから分からないことや理解できなかったことを質問していいですか?」とお願いするのも一つの手だと思います。
現場で緊張状態の中、色々な事を教わっているとその内容をメモを取ることでいっぱいいっぱいになってしまったり、頭がパンク寸前だったりして質問するどころじゃないと思います。
なので、一度家に持ち帰って手渡されているであろう資料やマニュアルやその日教わったことをメモをしていると思うのでそのメモを読み直す、その日の行動を思い浮かべてその中で「?」って思う事があればそれを箇条書きする。
そういった事をすれば中にはこれってどういう意味なんだろう・この介護の仕方の理由ってなんだろう?などと色々な疑問なんかが出てくると思います。
その内容を後日先輩職員に質問するといいと思います。
新人職員がぶつかる悩みと解決法

人間関係の悩み
介護の現場だけの問題ではないのですが、先輩職員の中には結構癖のある方もいます。介護経験のない新人職員に対して「仕事が遅い!」「こんなことも出来ないの!」なんて嫌味も言われることも珍しくありません。そういったことで人間関係に悩みを持つ新人職員も多くいます。そういった環境で潰れていく新人職員を多く見てきました。
対策としては、強いメンタルを持っている新人職員の場合は仕事になれ実力もある程度ついてくるころには癖のある職員もあまり小言を言わなくなってくると思うので最初の頃何を言われても気に留めずスルーする。※スルーっていっても無視するのではなくあくまでも話は聞いているって体で癖のある先輩職員に接してくださいね。
もう一つの対処法は、すでに威圧されすぎてもう辞めたいって感じている新人職員は辞めるって決める前に一度、上司などに相談することをオススメします。介護施設は複数のユニットやフロアーで構成されている事が多いので、他のユニットやフロアーに移動することも出来るので移動希望などを出して取り合えず今の環境から逃げる事もありだと思います。
健康・体力の悩み
介護職は体力のいる仕事です。慣れない環境での仕事となると心身疲労状態になりやすと思います。
また、介護は力仕事なので腰痛などを発症しやすくもなります。
対策としては、やはりきちんと休養と栄養を取りしっかりと疲れをとる。また、コルセットなど使用し体を保護する。それと、移乗介助など力を要する介助にはきちんと正しいやり方を身に着けることも大事です。
利用者との関係からくる悩み
認知症の利用者さんの対応などで最初の頃はどうやって接していいのか戸惑うと思います。また、利用者さんの中には「新人いびり」みたいなことをする方もいて心無い言葉を浴びせられたりもすることが稀にあります。
対策としては、最初の頃は積極的に利用者さんにかかわりその人の性格なのどの癖を把握すると次第にコミュニケーションを取りやすくなってきます。また、後者で述べた「新人いびり」の利用者さんに対しては概ね先輩職員も把握していることが多いので先輩職員に相談し対応してもらうと意外に問題解決するパターンが多いです。
仕事量での悩み
介護は実務の他に書類作成は雑務など多岐に渡り多くの業務をこなさないといけない職種です。
それに加え、早番・日勤・遅番・夜勤など交代制のシフトで生活サイクルも狂いがちになります。
新人職員のなかにはこの仕事量の多さでギブアップしてしまう人もいるくらいです。
本来であれば仕事になれるまである程度自力で乗り越えるのも社会人としての基本だとは思いますが、もう限界!って思い介護の仕事を辞めてしまうのはとてももったいないことだと思います。
対策としては、上司に相談し最初の頃は比較的業務量の少ない勤務帯に絞ってシフトを組んでもらう事をオススメします。私が今まで働いたことのある介護施設ではどの施設でもこのような方法で新人職員のフォロをしていました。
まとめ
介護の現場は常に手が足りない状態のことが多く、新人介護職員にも「即戦力」が求められます。また、他の介護職員も膨大な仕事を抱えていますから、新人だからといっても手取り足取り教えるといった心理的・時間的余裕がないことも多いです。
新人職員の方には「教えて欲しい」という自主的・積極的な姿勢を持つことも大事です。また、事前に介護に必要な基礎知識などを書籍や動画などで自分で勉強することも大事だと思います。
最後に、介護の仕事はとても大変ですが私はこの仕事を22年従事しています。世間では給料が安い休みが少ない、ブラックな職場ばかりなどの情報が多く出回っていますが、全てがその様な環境ばかりではありません。給料に関しては実力を付ければ交渉することも出来るのでそこまで心配することではないような気がします。私の場合はそうしてきました。
また、仕事に疲れていても利用者さんやご家族から励ましの言葉などを多くいただけます。結構それが励みにもなるんですよね。
現状では若い世代の介護士さんが少ないので出来ればもっと増えてもらえると現場も活気が付くと思うので是非!介護に興味のある若い方は介護施設などに見学に行かれることをオススメします!!